[amazon]THE AMERICAN CLAVE RECORDINGS [3CD]
アルゼンチン・タンゴに革命を起こしたアストル・パンタレオン・ピアソラ(1921-1992)。
ピアソラの作品はクラシック音楽とジャズとタンゴの要素が混ざり合って出来上がったものが多いです。
今回は、ピアソラ作品の中でも比較的大きな作品である『ブエノスアイレスのマリア』と『ブエノスアイレスの四季』について、解説していきます。
楽曲構成や聴きどころなどについても触れているので、ぜひ参考にしてみて下さい。
小オペラ『ブエノスアイレスのマリア』(1968)
ピアソラが作曲した中でも最も規模が大きく、またピアソラにとって一つの転換となった作品でもあります。
作曲背景
1959年に最愛の父を失ったピアソラは、どこか精神的不安を見せるようになりました。
それが魅力的な女性への逃避行へと繋がったのでしょうか、不倫が原因で1965年に23年連れ添ったデデと離婚することになります。
デデとの離婚原因になった女性は、その後もピアソラの悩みの種となりました。
この女性のためにすっかり精神的に消耗し、作曲にも身を打ち込めなくなったピアソラは廃人同然になってしまいます。
そんな中、詩人で熱心なタンゴ研究家であったオラシオ・フェレールがピアソラを訪ね、合作を持ちかけます。
精神的に不安定だったピアソラは、アルゼンチンでも屈指の占星術師を訪ね歩き、このことを占ってもらいます。
吉とでたからと作曲を始めたピアソラですが、いつしか主人公に自分自身が作り出そうとしている「新しいタンゴ」を重ね、その将来をオペラに委ねてしまったのです。
このオペラは内容が非常に難解で、よく分からないという人もいるぐらいですが、書いた本人の精神状態を考えれば、難解なものになっても仕方なかったのかもしれません。
オペラの内容
第一部
主人公のマリアは、アルゼンチンの片田舎に生まれ、一週間で成人します。
ブエノスアイレスの都会に憧れを持つマリアは、夜の街へと出掛けるようになります。
しかし、バンドネオンの音楽によって堕落してしまい、終いには下水溝の地獄に落ちて死んでしまうのでした。
第二部
マリアの葬儀が執り行われます。
しかし、マリアの肉体から離脱した「影」の存在は、街をさまよい続けました。
昼間は精神科医のところに出入りし、ありもしない話や妄想を話、精神科医を混乱させます。
夜になれば夜の街で遊び、ついにマリアは小悪魔の子を身籠ってしまいます。
そして、日曜日の朝、建設中のビルで子供マリアを出産するのでした。
小悪魔との子マリアの行く末については書かれていません。母マリアと同じ運命をたどるのか、それとも新しい活路を切り開くのかは分かりません。
オペラの中で語られる物語の意味とは
このオペラの主人公マリアは人であって人ではありません。
マリアは、ピアソラが作ろうとしている「新しいタンゴ」を人間化したものだったのです。
「新しいタンゴ」は生まれたものの、誹謗中傷に晒され、受け入れられなかった。
しかし、チャンスがあるのならば受け入れてもらえるのか。
そんな意味合いが込められています。
「新しいタンゴ」が人であったならば、こんな人生を送っていると暗に示唆したかったのがよく分かります。
曲について
オペラの構成をとっているため、クラシック要素は強いですが、ほどよくタンゴが混じり、主人公の感情の激昂などが美しく表現されています。
劇中歌の中には有名なものもあり、単品で歌われることもあります。
「受胎告知のミロンガ」や「フーガと神秘」などは特に有名です。
今作は、クラシック音楽の中でも特に古典的なフレーズを多く聞くことが出来ます。
『ブエノスアイレスの四季』(1965)
ヴィヴァルディの『四季』に着想を得て作曲したとされる作品です。
作曲背景
古典音楽へ回帰しているところで、ヴィヴァルディの『四季』を偶然コンサートで耳にしたピアソラは、これに着想を得て、『ブエノスアイレスの四季』を作曲することにしました。
着手したのはまず『夏』でした。
しかし、ここで大きなスランプに陥ったピアソラはしばらく作曲を中止し、期間をあけて『秋』、『冬』、『春』の順で作曲しました。
ヴィヴァルディの『四季』との比較
ヨーロッパと南アメリカ大陸の季節は真逆になります。
つまり、ブエノスアイレスが夏ならば、ヨーロッパは冬です。
このことをピアソラはしっかり楽曲に入れています。
ピアソラはまず初めに着手した『夏』にヴィヴァルディの『冬』のメロディを一部引用し、アレンジを加えているのです。
全体的にはタンゴ要素が耳によく響く曲なので、しっかり聴いていないと分からないという人も多いかもしれません。
五重奏用の曲
『ブエノスアイレスの四季』は五重奏で演奏されることが多いです。
ここでいう五重奏とはハンドネオン、ピアノ、ヴァイオリン、コントラバス、エレキギターです。
しかし近年は、ヴァイオリンとチェロ、ピアノの三重奏でも演奏されることが増えたようです。
ヴァイオリンがハンドネオン部分を担うので、よりクラシカルに聞こえることでしょう。
まとめ
いかがでしたでしょうか。
今回は、ピアソラの大好きなブエノスアイレスにまつわる2つの曲を選んで、ご紹介してきました。
ピアソラは古典音楽やクラシック音楽全体へのリスペクトも高く、各曲で味の効いた引用をすることでも知られています。
そんなピアソラがちょっとスピリチュアルな傾向に走った不思議な作品が『ブエノスアイレスのマリア』でした。
音楽自体は耳心地よく、アリアパートは心に響くメロディも多いです。
しかし、内容が内容だけに、話の筋がよく理解できないという人は少なくありません。
もし、このオペラを見る機会がある場合は、事前にストリーをしっかり読んで理解しておくことをお勧めします。
>>アストロ・ピアソラってどんな人?出身やその生涯は?性格を物語るエピソードや死因は?


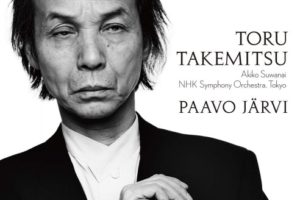

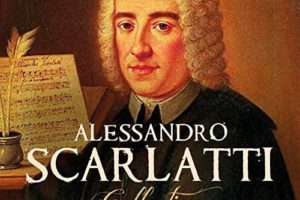
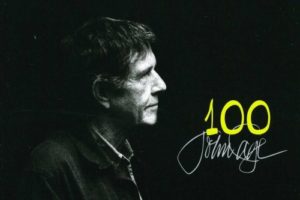
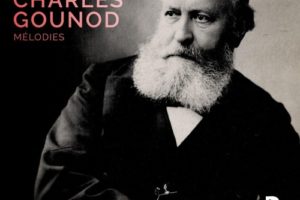
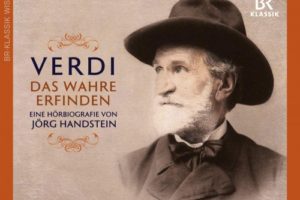
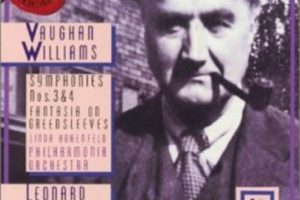
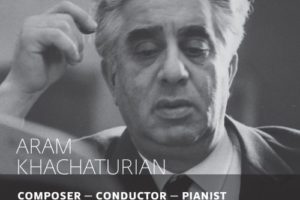



コメントを残す