ヨハン・セバスティアン・バッハ(1685~1750)(以下バッハ)は、神聖ローマ帝国(現在のドイツ)で生まれました。65年という人生の中で1000曲以上も作曲したと言われており「音楽の父」とも呼ばれていました。作曲家には誰にでも特徴や音楽の傾向が異なります。
逆に捉えると、作曲家それぞれの個性を出さないと音楽界では生きていけません。それは、作曲家に限らずアーティストにも言えることだと思います。似たようなことをやっても売れることはできませんよね?今回はその中でもバッハの曲の特徴をお伝えしたいと思います。
楽曲の特徴

まず初めに対称性についてです。バッハの曲には沢山用いられています。例でいうと、ピアノ曲「2声のインベンション BWV772」の中にある一節で、最初に右手で弾いたメロディを次は左手で弾いたり、オクターブあげて弾いたり、5度平行移動して弾いたりと同じメロディを演奏することです。
同じメロディの繰り返しだと飽きてしまいがちですが飽きさせずにこの要素を使うバッハは偉大です。他の作曲家の方にも見られますが、特別バッハはこの対称性という要素をふんだんに使っているので特徴と言えるでしょう。
2つ目の特徴としては、あえて新しいことはせずに既存の楽器を用いて作曲活動を行っていたことです。バッハの生きていた時代というと、ピアノも今の形ではなくまたオーケストラの楽器もほぼありませんでした。しかし、バッハの作った曲は今のオーケストラで演奏しても怠るどころかより輝いて聞こえる作風を用いているからだと思います。
やはり、新しい楽器が登場することにより昔の曲を演奏すると「昔の楽器だからできた音色を今の楽器では表現することが出来ない」などという結果は想像ついてしまいますよね。
私自身も、沢山のクラシック曲をさらってきましたがやはり「作曲家が求めているだろうという音色」を出すことは到底難しく、やはりその時にある楽器を想って作曲しているので無理もありません。
しかし、バッハの曲は「物足りない」と思わせることが少なくこの先にできる楽器を予想していたのではないかというくらいぴったりと今の楽器ではまっているのが聴いていて感じます。これも、バッハの音楽の特徴の1つだと言えると思います。
ここまで、2つの特徴を書かせていただきました。少し長くなってしまったので簡単にまとめると、対称性を曲中に沢山用いるが飽きさせない工夫がされており、約270年前に作曲した曲を今の楽器でも演奏することが可能な曲の作り方がバッハの一番の特徴だと私は思います。
おすすめ代表曲
では、次は話を少し変えてバッハの代表曲おすすめ5曲をお伝えしたいと思います。
トッカータとフーガニ短調BWV565
この曲は知らない人はいないのではないかというくらいなじみのある曲です。音楽の授業にも教材として取り上げられるほど濃い1曲になっています。オルガンのために作られた曲のため、今でもオルガンがあるコンサートホールや教会などでも演奏されます。また、曲名にある「トッカータ」は音形の変化を伴った即興的な楽曲という意味で「フーガ」は1つ、複数の主題が次々に模倣、反復される楽曲の形式のことです。そのため、最初のメロディは何度も出てきますね。
マタイ受難曲
受難曲とは大規模な声楽曲であり、キリストの苦難と死が語られています。バッハは他にも受難曲を残しましたが比べ物にならないくらい偉大な曲です。しかし、バッハの死後この曲はなんと80年もの間演奏の機会を失ってしまいましたがフェリックス・メンデルスゾーンにより世の中に飛び回るようになりました。壮大なスケールで人間愛が書かれたこの作品は時代を越え沢山の人の心に寄り添いました。
ブランデンブルク協奏曲
バッハは西洋音楽界でいう「バロック音楽」というカテゴリーに分類されます。バロック音楽の作曲家は「バロック協奏曲」という分類の曲を沢山作曲していました。しかし、バッハは6作品しか残していません。しかし、構成などが異なり普通は3楽章構成の急―緩―急でしたが、トランペットの超絶技巧を入れたり、あえてヴァイオリンを外すなど普通では考えられないことを取り入れ6曲あるうち1つとして同じ曲は存在しなかったためバッハは6曲しか残せなかったのかもしれませんね。
G線上のアリア
この曲は、バッハが作曲した「管弦楽組曲第3番ニ長調BWV1068」の第2曲目「アリア」をヴァイオリン独奏のためにヴァイオリニストが編曲した曲です。「G線上」というのは、ニ長調からハ長調に移調して編曲したため、ヴァイオリンの4弦あるうちの最低音、G線のみで演奏できることから由来しています。TBS系のドラマ「G線上のあなたと私」のヒロインがヴァイオリンを始めるきっかけになったのがこの曲なのです!
アヴェ・マリア
この曲、実は作曲したのは「バッハ」ではなくフランスの作曲家「シャルル・グノー」でした。バッハが作曲した「平均律クラヴィーア曲集」の「第1番 前奏曲とフーガハ長調」の冒頭部分を伴奏に用いて、グノーが作曲したメロディを上にのせて発表した曲です。しかし、元のバッハの作曲がなかったらこの作品は生まれませんでした。「グノーのアヴェ・マリア」とよく聞きますがバッハの「前奏曲とフーガのハ長調」ありきの曲ですね。
まとめ
今回は、バッハの作品の特徴と代表曲おすすめ5選をご紹介させていただきました。はっきりとした根拠はあまり残っておらず謎多き人物のため研究者も頭を悩ましているかもしれません。しかし、作品の傾向や特徴を見ているとバッハ自身様々な経験をしたため様々なジャンルの曲を作曲したことが分かりますね。今回は、5選しかご紹介できませんでしたが他にも何百曲と書いたバッハはまさに「音楽の父」ですね。
👉〔amazon〕ヨハン・セバスティアン・バッハのCDはこちら。
>>ヨハン・セバスティアン・バッハってどんな人?その生涯や性格は?

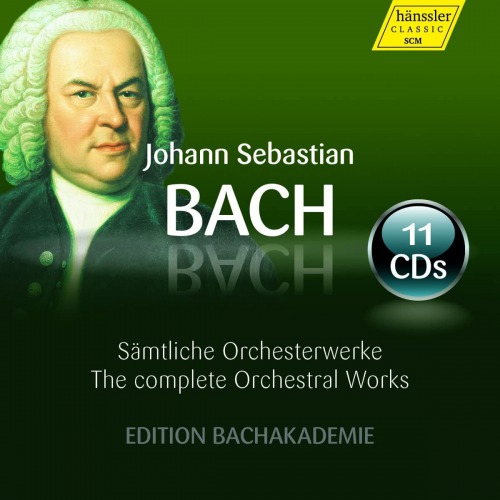

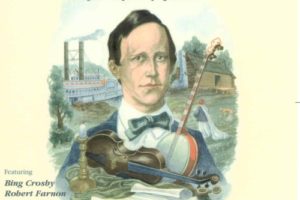
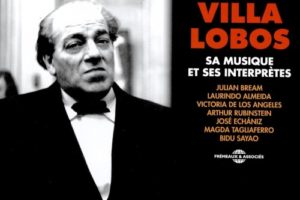
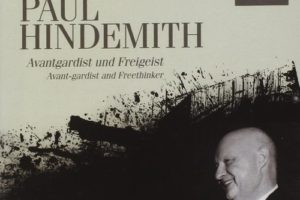
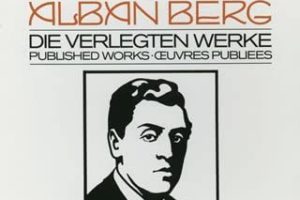

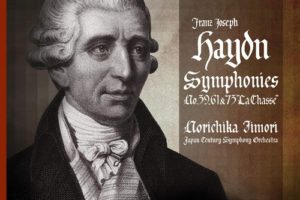



コメントを残す