出典:[amazon]Handel Edition (65CD)
今回は、ゲオルク・フリードリヒ・ヘンデル(1685~1759)(以下ヘンデル)といえばこの曲と言ってもよいほどの代表作オラトリオ「メサイア」について解説や分析、構成、聴きどころについてまとめたいと思います。作曲は1741年9月に始めました。約2時間半の大作ですがヘンデルはなんと24日間で作ったと言われています。また、楽曲は3部構成になっています。
そもそも、「オラトリオ」というのは、キリスト教を題材としオーケストラがバックで演奏し独唱や合唱などの歌を用いて劇的に構成したものを言います。簡単に言えば、衣装や道具を一切用いらない「オペラ」とも言えます。「メサイア」という言葉は訳すと「救世主」という意味になります。
そのため、キリストの一生を描くよりも全人類の救世主としてキリストの存在を訴えについて歌った楽曲になっています。
解説
第1部「救世主生誕の予言と、降臨」
(メシア到来の準備2~4曲目)
序曲から始まり、2曲目から歌が始まります。「救世主が現れ戦争状態であったエルサレムが赦され民が慰められる」という予言を歌います。
(予言5~7曲目)
神の言葉として「天地、国を揺り動かそうとするとメシアはやってくる。」(5曲目)と伝えに来ます。続くアリア(6曲目)では「メシアは炎のようにすべてを焼き尽し清めてしまう」と歌い次の合唱(7曲目)では「清めたものだけが捧げものが出来る」と歌い、キリストが生まれるにふさわしい土壌が整備されます。
(受胎の知らせ8曲目)
ここでは受胎の知らせとメシアが到来し喜ぶシーンになっています。
(闇の中の光9~10曲目)
この2曲は喜びというよりは栄光が現れる前の闇の中に光が差すとお膳を立て次から始まるイエスの誕生の喜びをさらに際立たせています。
(生誕11曲目)
イエスが生まれた喜びを合唱にて「私たちのために生まれてきた」と歌います。
(田園曲12曲目)
イエスが生まれた田園を思い浮かべるようなのどかな器楽曲が流れます。
(降誕の知らせ13~15曲目)
羊飼いの所に天使がイエスの誕生を伝えに行きます。
(イエス到来の喜び16曲目)
救世主を得たエルサレム(シオン)の人々の喜びをソプラノが歌いあげます。
(主の栄光17~21曲目)
イエスが生まれた奇跡や生涯について簡単に語っています。
第2部「受難と贖罪そして復活」
(人々の裏切り19~20曲目)
場面は一転し、十字架を担いで丘を登るイエスを思わせる思いリズムが特徴です。イエスが人々に認められずのけ者にされても顔を隠すことはなく全て受け入れていたことを歌います。
(贖罪による救済21~23曲目)
救世主が病や苦しみを負うことにより人類は救われると3曲合唱で歌います。
(あざけり24~25曲目)
イエスをあざ笑う民衆をテノールが歌い、続く合唱でも「彼は神を信じている、それなら神が助ければよい」と歌います。
(絶望と処刑26~28曲目)
イエスは自分を慰めてくれる人を見つけることが出来ず「命あるものの地から断ち切られる」と歌い十字架上でイエスは死にます。しかし、この時に「死」という言葉は直接出てきません。
(復活の福音のひろがり29~34曲目)
神イエスを見捨てていなかったこと歌い、一度冥府に落ちたイエスの魂が復活するための城門を開けるための合唱が歌われます。
(平和の福音34~35曲目)
福音が伝えられていく様が美しいメロディにより歌われ、福音、伝道が世界の隅々にまで行き渡ることを歌います。
(地上の王たちの反乱36~37曲目)
ここでは抵抗勢力が登場し弾圧する王たちの姿を歌います。
(天上のあざわらい38曲目)
地上の王たちのむなしい抵抗を天の神々があざわらいます。
(全能の王の賛美39曲目)(ハレルヤ)
抵抗勢力を打ち砕き、栄光の国が現れたことを賛美する合唱です。
第3部「永遠の生命」
(復活への信仰40~41曲目)
キリスト教信仰の根幹をなす「復活」への信仰を歌いあげます。
(永遠の生命42~43曲目)
トランペットとアリアの掛け合いにより「最後のラッパが鳴ったら死者は朽ちざるものへと蘇る」と永遠の生命への変容を高らかに歌い上げます。
(死に対しての勝利44~46曲目)
「死は勝利に吞まれてしまった」と死の敗北を歌い次の45曲目で対句表現として「私たちは勝利を賜った」と歌います。
(屠られた子羊(イエス)に対する賛美、アーメン47曲目)
人間の原罪を負って受難し、人間を救ったイエスを讃える賛歌を歌い幕が閉じます。
分析

全体を通して言えることは、「アリア→合唱」という構成になっていることです。合唱を用いることにより伝えたいことを歌にのせて迫力を増して伝えることが出来ます。また、バックのオーケストラもごくわずかで限られているため、オーケストラが前に出ず歌を主役としていることも分かります。しかし、ずっとバックでいるのではなく必要な時にはしっかりトランペットや低音が聴こえるようにするための工夫が楽曲の中に組み込まれているため、十字架を背負って丘を登るイエスの重い足取りなどを表現しています。
とても24日間では作ったとは思えないほど盛り沢山の構成となっていますがやはり「ここを伝えたい」というところをしっかりと合唱やオーケストラを用いることによりそれを現実的に伝えることが出来ているのが「メサイア」の1番の特徴だと思います。
楽器構成
バックで演奏するオーケストラはやはり普通のオーケストラ編成とは異なり、オーボエ、ファゴット、トランペット、ティンパニ、弦楽器、通奏低音が用いられ、ソプラノ・アルト・テナー・バスの各独唱と、混声合唱団により構成されています。
聴きどころ

まずは、なんといっても第2部の最後に歌われる「ハレルヤ」です。この曲はテレビ番組のBGMとしてもつかわれることがあり知らない人はいないのでは?というくらい聴きなじみのある曲です。ちなみに「ハレルヤ」の意味はヘブライ語で「神を賛美せよ」という意味です。この意味の通り抵抗勢力に打ち勝ったことを歌っている場面になります。
また、どの団体も同じ楽器や演奏方法を行うのではなく、指揮者が聖書等を読み漁り「ここはこの方がより効果が出る」と判断し独自の強弱などを用いている団体も少なくありません。仮に同じメンバーで構成された団体でも指揮者が変わるとガラッと音楽も変わります。今ではCDを買わなくても音楽が聴ける世の中なので様々な指揮者や様々な団体の演奏を聴き比べるのも面白いと思います。
まとめ
長くなってしまいましたが今回はヘンデル作曲「メサイア」についてまとめさせていただきました。「メサイア」と聴くとあまりピーンとこなかった方もいたと思いますが「ハレルヤ」は聴いたことがあると思った方は少なくないと思います。また、「オラトリオ」というのはバロック時代によく作られていた形式のため普段触れ合う機会が少ない形式です。これを機に「メサイア」は勿論「オラトリオ」について触れてみるのも面白いかもしれませんね。
👉〔amazon〕ゲオルク・フリードリヒ・ヘンデルのCDはこちら。
>>ゲオルク・フリードリヒ・ヘンデルってどんな人?生涯や性格・死因は?

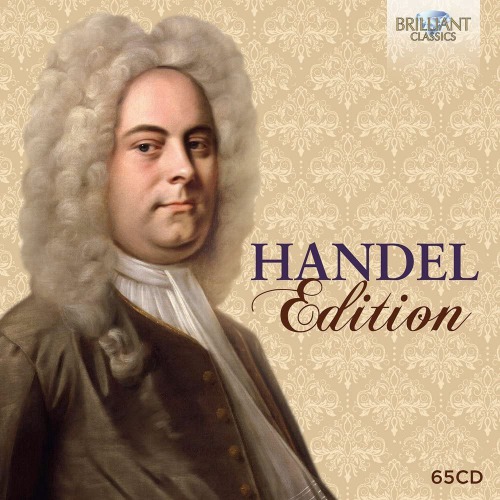

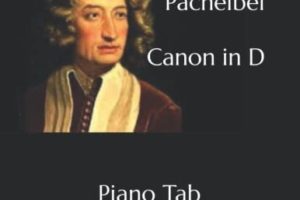
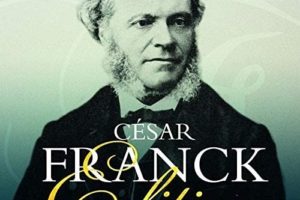
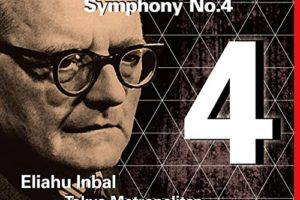
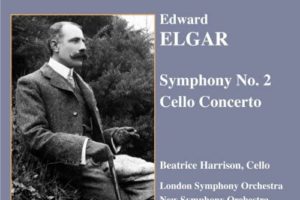
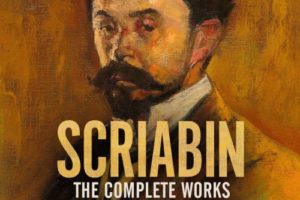
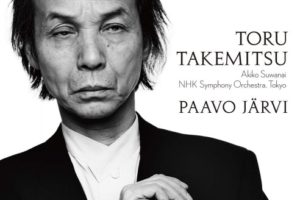
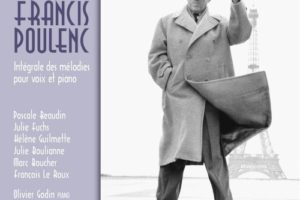



コメントを残す