アップライトピアノ、グランドピアノは弦の振動で音を出す楽器で、チューニングが必要になります。バイオリンやギターなどの楽器は自分でチューニングすることができますが、ピアノの場合は専門家である調律技術者が行います。使用による消耗や気温差や湿度差などによって音律にズレが生じますが、どれくらいの頻度で調律をすればよいのでしょうか。ピアノの調律についての解説と調律頻度についてご紹介していきます。
定期的な調律メンテナンスが必要

時間の経過とともに張られている弦は微妙に変化します。アップライトピアノでは鍵盤とハンマーをつなぐアクション部分だけでも鍵盤1つにつき80個ほどの部品が組み合わさっています。パーツ、部品の経年による変化などのチェックや、ピアノの弦の伸びなどをチェックしていきます。ピアノを数年弾いていなく放置していても弦は伸びていくので音程が乱れていきます。弦、ハンマー、鍵盤などひとつずつチェックして部品の動き方、音の高さを調整・調律することで、ピアノを心地よく弾くことができます。
88鍵(約230本の弦)
ピアノの鍵盤は88鍵あり、平均率という音階によって88鍵すべての音が定められています。調律がきちんとされているピアノを弾くと、単音で音を鳴らした場合音の揺れがなく、和音で弾いたときにもとても美しい響きになります。ピアノの弦の数は中音と高音は1つの鍵盤に対して3本ずつ弦が張っており、低音に近づくにつれて鍵盤に対して弦が減っていき、モデルにより多少の違いがありますが約230本の弦が張られています。弦1本あたりの張力は約90kgあり、調律しないと弦がゆるみ、音が狂ってしまいます。弦を一つずつ丁寧に調整するには経験も必要になります。
調律するときはどっち?ピッチ440Hzと442H
音程は、「ピッチ」(基準音)と呼ばれ、ピアノ調律の際、基準となるラ(A)の音をピッチとし、440Hz(ヘルツ)と442Hz(ヘルツ)が一般的なピッチです。日本の音楽ホールではラ(A)=442Hz(ヘルツ)で調律されることが多く、ラ(A)の音が1秒間に442回振動することを指します。440Hz(ヘルツ)より442Hz(ヘルツ)に調律されると音が明るく聴こえます。
「整調」「調律」「整音」
ピアノの調律は主に「整調」「調律」「整音」の3つの工程に分けられます。またピアノの鍵盤下や内部を掃除や、ペダルなどの状態をチェックします。定期的にメンテナンスをすることでピアノの音色もきれいになり、弾き心地よいものに維持することができます。
| 整調 | 鍵盤やアクションを微調整し、ピアノのタッチや響き、弾き心地を整える |
| 調律 | 音律を正しく合わせる |
| 整音 | ハンマーを整え、音色、音量などバランスよく整える |
同じ粒・音の響きのクオリティ・豊かな音色

ピアノ調律師の音色を整える「整調」という作業はピアノの弦を叩くハンマーに針を刺して、音色に深みと響きをつくっていきます。音楽性と高度な職人技術が要求される作業なので、調律師によって同じピアノでも異なった音色になります。クオリティのよい音の響きにするためには専門的知識だけではなく、技術、経験によって作り出されています。
湿度温度差によって変化する
ピアノは「スプルース」「カエデ」「ブナ」など木でできているので、ピアノの音律は湿度や温度によって変化します。エアコン、暖房機器や季節によって湿度や温度の変化で、音が狂いやすくなります。ピアノの弦は金属なので湿度が高すぎると錆びやすくなり部品の劣化がしやすくなります。最低な温度は15℃~25℃で、湿度は夏季40~70%、冬季は35%~65%が目安なので、湿度は50%前後に保つようにしましょう。人が過ごしやすい温度や湿度はピアノにとっても良い環境になります。
ピアノの音律は専門家にお任せしましょう

一台のピアノは、何千というパーツによって作り上げられており、他の楽器のように簡単に自分で調律することはできません。調律師によって、音程も音色もタッチも変わってきます。調律師の能力によって同じピアノでもまったく仕上がりが異なるくらいなので、調律師選びも慎重にする人もいます。非常に専門的な技術を要するので、一般社団法人日本ピアノ調律師協会会員である調律師を選ぶと良いでしょう。
定期的な調律でメンテナンスをしましょう
新品のピアノは弦が安定していないので音が狂いやすく、購入してから数年は1年に2回程度の調律をすることをお勧めします。ある程度使用しているもの、また普段使っていない場合も1年に1回は調律をしておきましょう。ピアノを移動させると音が狂いやすいので、部屋の模様替え時や引っ越しなどでピアノを動かした場合には調律が必要です。ピアノを普段使っていないからといって放置していると、ピアノの寿命が確実に縮まり、大掛かりな修理が必要になることもあるので、定期的に調律をしておきましょう。








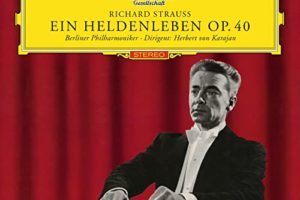




コメントを残す