出典:[amazon]カミーユ・サン=サーンス/CAMILLE SAINT-SAËNS
カミーユ・サン=サーンスという作曲家をご存知ですか?サン=サーンスはフランスを代表する作曲家であり、同じくフランスの作曲家フォーレの先生でもありました。ピアノ、オルガン、作曲に非凡な才能を発揮し、幼少の頃は「モーツァルトの再来」と評された人物です。サン=サーンスが作曲した「動物の謝肉祭」の「白鳥」や「水族館」は、ドラマなどでも使われることがあり、大変人気のある曲です。今回は、今年で没後100年を迎えるサン=サーンスの生涯や性格について解説します。
サン=サーンスの生涯

サン=サーンスの生涯をご紹介します。サン=サーンスは86歳という当時としては高齢で、その生涯にはさまざまなことがおきました。ここではその生涯を大きく3つの時期に分けて解説します。
幼少期からパリ音楽院時代
カミーユ・サン=サーンスは1835年フランスのパリで生まれた、19世紀から20世紀初頭を代表するロマン派の作曲家です。生後わずか2ヶ月で父を亡くしたサン=サーンスでしたが、母と大叔母に育てられ、幼少期から音楽に対する非凡な才能を発揮しました。2歳でピアノを始め、わずか10歳でベートーヴェンやモーツァルトを演奏してコンサートデビューしました。1848年に13歳でパリ音楽院に入学。ピアノ、オルガン、作曲を学び、その才能はますます開花していきます。17歳で作曲した「交響曲第1番」は作曲家グノーから高く評価され、発表した教会での演奏会は大盛況だったそうです。
教会オルガニスト時代から50歳まで
1857年、22歳のサン=サーンスはマドレーヌ教会で専属のオルガニストに任命され、以降20年間オルガン奏者を勤めることになりました。それと同時に、4年間にわたって音楽大学でピアノ教師として教壇に立つことになり、教え子の中には作曲家のフォーレもいました。
この時期のサン=サーンスは、若手作曲家の育成のために国立音楽教会を設立するなど、その後のフランス音楽発展に大きく貢献しました。
また、オペラの作曲を多く手がけており、1883年47歳で作曲した「ヘンリー8世」は大変な人気を博しました。そして、50歳になると、サン=サーンスの一番の代表作である「動物の謝肉祭」を発表します。プライベートでは40歳のときに教え子だったマリ=ロール・トリュホと結婚し2人の子を授かりますが、残念なことに2人とも亡くなってしまい、妻のマリとも離婚となりました。
晩年
サン=サーンスは、その長きにわたる業績が讃えられ、ケンブリッジ大学から名誉博士号が授与されたり、ドイツや母国フランスから勲章を贈られるなど、名誉ある晩年を過ごしました。プライベートでは、1888年に母を亡くした後、旅行をしながら生活したことで知られています。なかでも特にアルジェリアがお気に入りだったようで、たびたび訪れていたそうです。アルジェリアに対する思いはサン=サーンス自信が作曲した管弦楽「アルジェリア組曲」に込められています。
また、晩年のサン=サーンスの功績の一つに映画音楽の作曲があげられます。映画「ギーズ公の暗殺」という作品の音楽を担当したサン=サーンスですが、これは作曲家が映画音楽を全て担当した最初の作品と言われています。数々の功績を残したのち、1921年の12月、サン=サーンスはアルジェリア旅行中に86年の生涯に幕を下ろしました。フランス音楽界だけでなく、後世の音楽に多大な影響を与えた作曲家の葬儀は、その栄誉を讃え国葬で執り行われました。
性格

サン=サーンスは、人に対して辛辣(しんらつ)でしばしば無頓着であったようです。それは彼自身があまりに天才であったためかもしれません。この性格を表すエピソードに次のような話があります
20世紀を代表するピアニスト、アルフレッド・コルトーがパリ音楽院在籍中にサン=サーンスが視察に訪れました。そのときサン=サーンスはコルトーに対して「君の選考は?」と聞きます。「ピアノです」と答えたコルトーに対してサン=サーンスは「君が?冗談を言ってはいけないよ」と皮肉たっぷりに言ったそうです。
真偽はわかりませんが、サン=サーンスの皮肉屋っぷりがよくわかるエピソードで、クラシックファンならご存知の人も多いかもしれません。
逸話

サン=サーンスは、逸話の塊といってもよいほどの天才でした。たとえば、2歳のサン=サーンスがあまりにピアノに熱中するので、母がピアノに鍵を掛けたという話が有名ですが、わずか2歳にして、幼児用のピアノ教本を1ヶ月で終わらせてしまったという伝説も残っています。
それだけにとどまらず、3歳ですでに作曲もしていたようで、天才モーツァルトより作曲開始年齢が早いことから「モーツァルトの再来」とまで言われました。
ピアノやオルガンの腕前も超一流で、フランツ・リストの前でオルガンの即興演奏を披露したところ「世界でもっとも素晴らしいオルガニスト」と絶賛され、これ以降リストとの交友関係が続くようになりました。
サン=サーンスの才能は音楽以外にも発揮されました。子供の頃からギリシャ語やラテン語を読みこなす秀才でもあったそうで、言語の他にも天文学、数学、哲学、文学などに精通し、それぞれ分野で論文を書いてしまうほどの人物でした。このことから、サン=サーンスは文化人としても活躍していたことがうかがえます。
まとめ
いかがでしたか?今回はサン=サーンスの生涯や性格についてご紹介しました。音楽だけではなく、多岐にわたって才能を発揮したサン=サーンスは、近代フランス音楽を語る上で欠かすことのできない人物です。性格は多少気難しいところがあり、皮肉たっぷりの人物だったようですが、その音楽は形式を重んじながらも繊細な美しさに溢れています。ぜひこれを機に、サン=サーンスの音楽に触れてみてはいかがでしょうか。

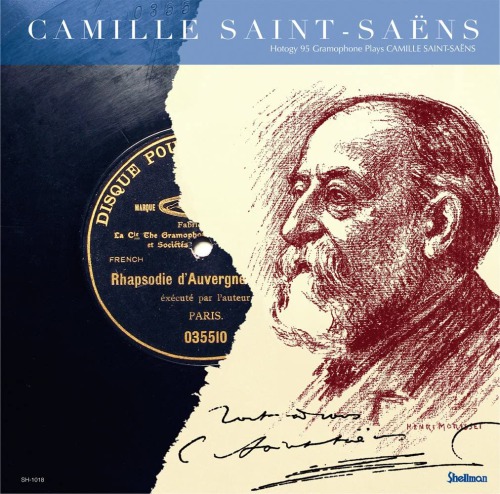
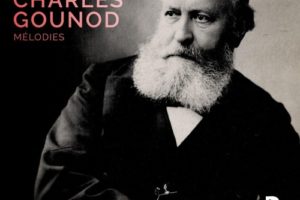
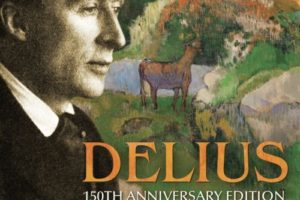
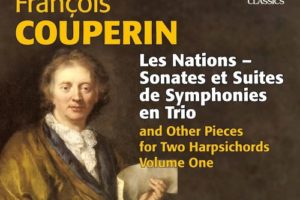
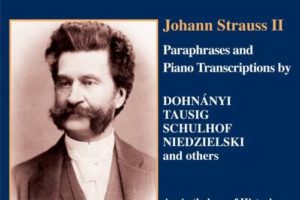
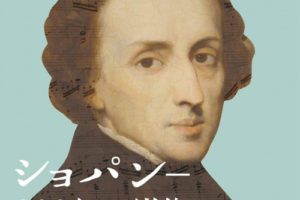
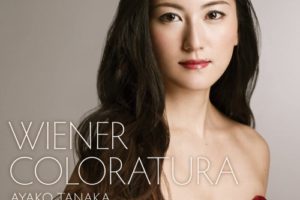
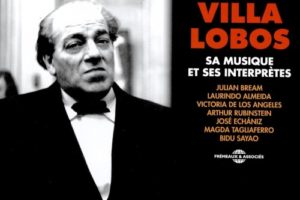
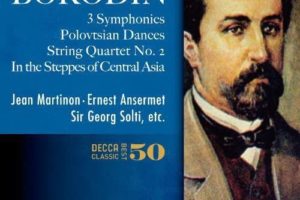



コメントを残す