[amazon]ベートーヴェン:交響曲第7番 (Beethoven: Symphony No.7)
カルロス・クライバーは、20世紀後半から21世紀初頭にかけて世界的に活躍した指揮者です。オーストリアの名門ウィーン・フィルハーモニー管弦楽団の首席指揮者を務め、その華麗な音楽性と情熱で世界中のクラシックファンを魅了しました。またクライバーは、その繊細な音楽解釈と緻密なリハーサルによって知られ、常に音楽作品の本質を追求し、指揮者の歴史に大きな足跡を残しています。情感豊かでありながら技術的にも優れ、特にベートーヴェンの交響曲やブラームスの作品などにおいて高い評価を獲得し、現在でも名盤の1つとして数えられています。
そこで今回は、20世紀最高の指揮者と称されるカルロス・クライバーの生涯を解説します。
カルロス・クライバーの生涯について

カリスマ的人気を誇ったカルロス・クライバーの生涯について解説します。大指揮者を父に持ったことで、その生涯には常に父の影が見え隠れしていたようです。
幼少期から才能を発揮するものの
カルロス・クライバーは1930年7月3日、父エーリッヒ・クライバーと母ルース・グッドリッチの子としてベルリンで生まれました。クラシック音楽ファンの方はご存じかもしれませんが、エーリッヒ・クライバーはアルバン・ベルクのオペラ『ヴォツェック』などの初演を務めた大指揮者です。
幼少期、クライバー一家はアルゼンチンのブエノスアイレスに移住し、クライバーは少年期をアルゼンチンにて過ごしています。父の才能を受け継いだクライバーは、少年時代から作曲や歌の才能を示し、父と同じく音楽家の道を期待されます。
そんなクライバーの才能について父エーリッヒも気がついていたものの、自分と同じ道を歩ませたくないという思いから、音楽の道に進むことに反対したそうです。
その後、父の意向通りチューリッヒ工科大学で化学を専攻したクライバー。しかし音楽の道を諦めきれず、大学を中退し音楽に専念することを決意し、1954年にポツダム劇場にて指揮者デビューを果たします。
フリーランスの指揮者として
指揮者デビューとなったのち、たちまち評価を高めたクライバーは、1958年から1964年までをドイツで、1964年から1966年までをスイスのオペラ座で指揮し、さらに1966年から1973年をシュトゥットガルトの楽長として類い稀な手腕を振いました。
しばらくはドイツ国内の歌劇場で指揮をしたクライバーですが、その後は常任指揮者に就任することなく、客員指揮者として世界中のオーケストラと共演を果たしています。
そのなかでも印象的なのは、1966年に行われたエジンバラ音楽祭でのイギリスデビューでした。このときの演目は、父エーリッヒが1925年に世界初演を行ったアルバン・ベルク作曲のオペラ『ヴォツェック』。この演奏が世界的な評判となり、クライバーの人気は揺るぎないものとなりました。
また、1978年にはシカゴ交響楽団と共演しアメリカデビューも果たしています。
晩年のクライバー
もともとコンサートに登場することも少なく、キャンセル魔でもあったクライバー。そんな彼は、1980年代後半を境にますます表舞台から姿を消し始めます。この時期にクライバーが指揮した回数は、良くて年に3回。それでもクライバーが指揮するとなると、大きなニュースになり大勢の人が彼を目当てにコンサートに訪れたそうです。
しかしその後、1999年になり完全に沈黙したクライバーは、同年1月と2月にバイエルン交響楽団を指揮したのを最後に、指揮者としての舞台から姿を消すことになりました。そして2004年、前立腺がんの闘病ののち、74歳でこの世を去っています。
カルロス・クライバーのエピソードは?

カルロス・クライバーのエピソードについて紹介します。彼の父エーリッヒ・クライバーも名指揮者であったことから、父と比べられることに葛藤したと言われています。
インタビュー嫌い
インタビュー嫌いとして知られたクライバー。指揮者としてのデビュー以来、その生涯を終えるまで、たった1度しか公の場でのインタビューを受けなかったそうです。
しかもそのやりとりも「クライバーさん、あなたはシンフォニーだけではなく、オペラも指揮なさるのですか?」との質問に対し「たまにやる程度です」の一言のみ。
あまりにぶっきらぼうな対応だったため周囲から顰蹙(ひんしゅく)を買うかと思いきや、コンサートが開かれる際には常にチケットが即完売するほどの人気ぶり。メディアへの露出が極端に少ないことが、クライバーがカリスマ的人気を獲得した理由の1つかもしれません。
巨匠たちも絶賛
20世紀を代表する名指揮者からも絶賛されたクライバー。なかでもカール・ベームは、当時の若手指揮者のなかで、クライバーただ1人を才能のある人物と評価しました。その後、ベームとクライバーは私生活でも親しくなりましたが、クライバーの性格について「気難しい男だよ、父親に似て」と冗談まじりに語ったそうです。また帝王カラヤンもクライバーについて「正真正銘の天才」と述べ、その才能を絶賛しました。
生涯最後のオペラ公演は日本で行われた
1974年に初来日を果たして以来、4度にわたり日本公演を行ったカルロス・クライバー。なかでも1994年に来日した際に指揮をした、リヒャルト・シュトラウスのオペラ『バラの騎士』の出来について「生涯最高の『バラの騎士』の演奏ができた」と、満足げに語っていたそうです。しかし残念なことに、これ以降、来日することは叶わず、さらには彼にとって生涯最後のオペラ公演となりました。
ユーモア溢れる人物
こちらも日本での出来事。プッチーニのオペラ『ラ・ボエーム』を上演中、ヒロインのミミが最後の力を出し切って歌い上げる名シーンで事件はおきました。作品の中でも屈指の場面であるその時、なんと突然、ロバの鳴き声が会場中に響き渡ります。ロバの登場シーンは第2幕。本来であれば幕が終わった後、会場の外にロバを待機させるはずが、その日は雨だったため、気を利かせたスタッフがロバが濡れないように中に入れておいたそうです。なんとかオペラ上演は終了したものの、周りのスタッフはクライバーが怒るのではないかとヒヤヒヤしたと言います。
しかしそんな状況でも、クライバーは怒る様子を一切見せず「今日は思いがけない二人目のテノールの競演というおまけがついたね」と語ったとのこと。クライバーのユーモアが伺えるエピソードです。
カルロス・クライバーの演奏風景
冒頭に書いたように、ベートヴェンやブラームスの作品で人気を博したカルロス・クライバー。なかでも筆者のイチオシは、なんといってもベートーヴェンの『交響曲第7番』です。弾けるような第1楽章、失意に沈む第2楽章、そして駆け抜ける第4楽章は、カルロス・クライバーの才能の全てが表現されているといっても過言ではありません。「ベートーヴェンってこんなに素晴らしいのか!」と改めて実感できる演奏ですので、まだ聴いたことのない方はぜひ聴いてみてください!
クライバーはメディア嫌いではあったものの、人生で2度「ウィーンフィルハーモニー・ニューイヤー・コンサート」に登場しています。シュトラウスの作品を好んだ貴重な演奏も併せてご覧ください。動画は1992年のものです。
まとめ
カルロス・クライバーの生涯やエピソード、演奏風景について紹介しました。大のメディア・インタビュー嫌いで、演奏会のキャンセルも少なくなかったクライバーですが、それでも彼が指揮するコンサートは毎回超満員の人気ぶりだったそうです。そんな彼は、カラヤンやフルトヴェングラーといった名指揮者を抑えて、20世紀でもっとも人気を獲得した指揮者とも言われています。残された録音はわずかではあるものの、どれも珠玉の名演ばかりですので、ぜひこの記事を機会に、カルロス・クライバーの指揮を聴いてみてはいかがでしょうか。



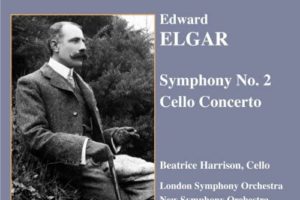

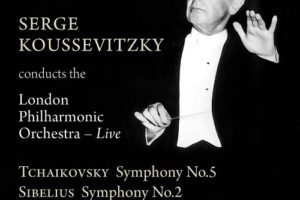


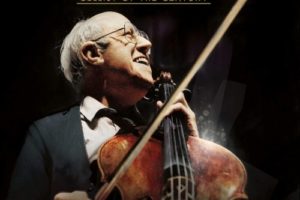




コメントを残す