出典:[amazon]Gustav Mahler: Complete Edition
作曲家としてだけでなく、当時はとても有名な指揮者としても忙しく活動をしていたグスタフ・マーラーは、ほとんど夏の休みの期間しか作曲に専念することができなかったようです。マーラーは、その短い期間に作曲を行っていたにもかかわらず、たくさんの代表作を残しました。その中から交響曲第5番について詳しく解説をしますが、マーラー自身についても前半部分で少し紹介していきます。
グスタフ・マーラーについて
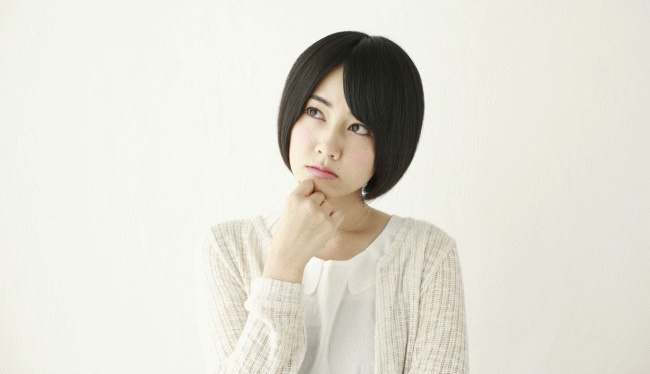
マーラーと言えば、交響曲や歌曲でよく知られている音楽家です。有名な指揮者としての活動を行いながらの作曲活動でしたが、マーラーにはユダヤ人ということからの苦労もあったと言われています。
生涯
1860年にボヘミアに生まれたマーラーは、14人兄弟の次男でした。しかし、長男が幼い頃に亡くなっていたことから、次男として生まれたマーラーが長男のように育てられたようです。
10歳でピアニストとして演奏会に参加し、音楽院に入ってからは演奏でも作曲でも賞を受賞しました。また、このころに作曲された「ピアノ四重奏」は、マーラー唯一の室内音楽として残っています。
音楽院卒業後は、様々な歌劇場で指揮者として活躍をしていましたが、それでも生活は苦しかったようです。マーラーが契約した主な所としては、カッセル、ドイツ歌劇場、ライプツィヒ、ブダペスト、ウィーン宮廷歌劇場、メトロポリタン歌劇場などがあげられます。指揮者としてだけでなく、中には芸術監督として活動を行ったこともありました。
1911年に50歳でマーラーは亡くなりますが、最後にモーツァルトの名前を呼んだというのは有名なエピソードではないでしょうか。
ユダヤ人として
有名な指揮者として活躍していたマーラーですが、ユダヤ人だったことで周囲から攻撃を受けることもあったそうです。マーラーがヨーロッパから出て行ったのは、その問題が大きかったと考えられています。
またユダヤ人ということから、マーラー本人が亡くなった後の反ユダヤの勢いにより、作品の演奏が行われなくなってしまいます。改めて評価されるようになるのは、その後数十年してからのことでした。
結婚
マーラーは19歳も年の離れたアルマという女性と結婚をしましたが、アルマは段々と精神的に状態が悪化していってしまいました。それには様々な要因が考えられますが、そのうちの1つに、作曲を行えなくなったこともあげられるのではないかと考えられています。実はアルマも作曲を行っていた音楽家でしたが、マーラーは結婚をする際にアルマに作曲を辞めさせていました。
そしてアルマは療養のために向かった場所で、若い建築家の男性と恋に落ちてしまいます。アルマは恋多き女性だったのか、マーラーが亡くなった後にこの男性と再婚をしますが、実はその時すでに別の画家の男性とも関係がありました。
マーラーの特徴的な作品
交響曲と歌曲で有名なマーラーの作品で、特に特徴的な作品をあげるなら、交響曲の「第3番」「第6番」「第8番」などではないでしょうか。それらには、過去に最長の交響曲としてギネスに載ったり、珍しい楽器の使用を行い、重要なシーンでハンマーが使用されたり、演奏人数が初演当時で1000人を超えたりという特徴があります。
またよく演奏される作品として知られているのは、交響曲の「第1番」と「第5番」です。
グスタフ・マーラーの交響曲第5番について
マーラーの交響曲の中でも演奏されることが多く人気の第5番について、まずは簡単に作品に関する紹介をします。
絶頂期の作品
マーラーの絶頂期は何度かあるとされていますが、この作品の作曲時期はそのうちの1つと言われています。第5番の前の第2番~第4番に関しては、同じ歌曲集から歌詞を使用した声楽が入っていますが、この第5番には声楽が入っていません。またこの第5番が完成された1902年は、マーラーと妻アルマの結婚した年でもあります。
映画でも使用された作品
第5番の第4楽章が、1971年のある映画に使用されました。この映画に使用されたことが、第5番の人気の理由の1つとしてもあげられます。
グスタフ・マーラー「交響曲第5番 ピアノ版」の解説
第5番の中でも、特に知られている第4楽章「アダージェット」部分の、ピアノ版について解説をします。細かい部分は楽譜にもよるので、この作品を演奏する際の、基本的なテクニックや表現についての紹介です。
難易度
どのようなアレンジが入っているかにもよるかもしれませんが、基本的には中級程度のレベルになっています。またスピードのある曲ではないため、レベルの高い曲に挑戦するのが難しいという方でも、しっかりと丁寧に練習することができるのではないでしょうか。
演奏に関する注意点
上記でスピードのある曲ではないと書きましたが、このようなゆっくりと演奏する作品の場合は、特に表現について気をつける必要があります。速く格好良く演奏するような作品であれば、指の細かなテクニックが要求されますが、ゆっくりとした表現力が必要な作品の場合は指のタッチや集中力も必要です。スピードのある作品の場合は自然と集中してしまうものですが、このような作品の場合は演奏中に集中力を維持できるように、自分で特に意識しなければなりません。
またゆっくりとした作品で更に注意をする必要がある点としては、音と音のつなげ方です。ペダルに頼りすぎてしまい、実際の鍵盤上での指が離れてしまうことのないように気をつけて下さい。このようなポイントも、作品の表現に影響を与えてしまいますので、大切なテクニックとして練習をする必要があります。


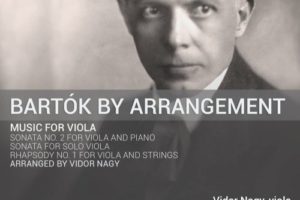
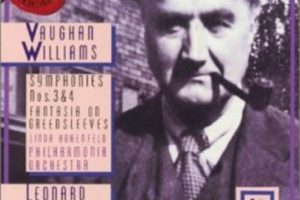
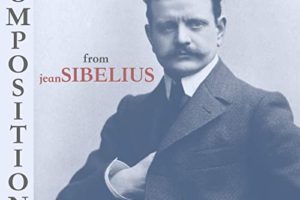
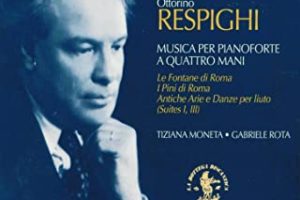

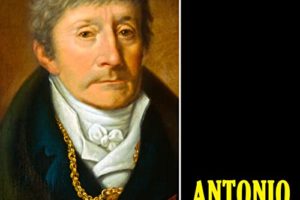

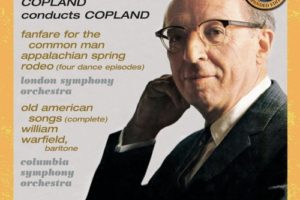



コメントを残す