今回は20世紀オーストリアを代表する指揮者エーリヒ・クライバー(1890-1956)について紹介します。ウィーンに生まれたクライバーは、ドイツ各地で指揮者としての経験を積んだのち、アルゼンチンでの常任指揮を経てフリーランス指揮者として世界各国で人気を獲得しました。
フルトヴェングラーやトスカニーニらと共に指揮者の黄金期を支えた人物であり、クライバーが指揮をしたビゼーの『カルメン』は、伝説的名演として現在も語り継がれています。
そんなエーリヒ・クライバーはどのような人生を歩んだのでしょうか。今回はエピソードを交えながら、その生涯を振り返ります。
エーリヒ・クライバーの生涯

1920年代の指揮者黄金期に活躍したクライバーですが、すべてが順調な指揮者人生とは言えませんでした。とりわけ「ヒンデミット事件」によりドイツを離れたことは、彼の人生において大きな転換点だったと言えるでしょう。
生い立ち
エーリヒ・クライバーは、1890年にオーストリアのウィーンに生まれました。父が教師だったため厳格な家庭に育てられましたが、家は必ずしも裕福な環境ではなかったようです。幼くして両親を次々と失ったクライバーは、母方の祖父母の元で少年時代を過ごしたのち、ウィーンに住む叔母のもとへ預けられます。
そしてこの頃から音楽を学び始めたクライバーは、グスタフ・マーラーが音楽監督を務めていたホーフオーバーでの公演に参加するなど、徐々に音楽との関係を深めたそうです。
マーラーの『交響曲第6番』の演奏に強い感銘を受けたクライバーは、指揮者になることを決意し、音楽家への道を志します。
その後ウィーンを離れプラハのカレル大学に通ったクライバーは、音楽以外にも哲学や美術史を専攻し、芸術への理解を深めます。1911年、幸運なことにドイツ劇場のコーチとして招かれた彼は、伴奏者としての仕事をこなしながら、音楽家への道を着実に歩み始めました。
ナチス・ドイツに反発して国外へ
ドイツ劇場で長年にわたり経験を積んだクライバーにチャンスが訪れたのは、1923年のこと。ベルリン国立歌劇場が後任指揮者を探していたところに、クライバーの名前がのぼります。当初このポストには、ブルーノ・ワルターやオットー・クレンペラーの名前が挙げられていたものの結論が出ず、同年8月、クライバーは晴れて指揮者デビューとなります。この時の演奏曲はベートーヴェンの『フィデリオ序曲』だったそうです。
ドイツ国立歌劇場でのクライバーの指揮ぶりは好評を博し、ヤナーチェクの『イェヌーファー』やアルバン・ベルク代表作『ヴォツェック』の初演を指揮したのもクライバーでした。とくに、ヤナーチェクの成功の影にはクライバーの功績が大きいとも言われています。
1926年、クライバーはアメリカ人のルース・グッドリッチと結婚し、2人の子を授かりました。のちに娘のヴェロニカは指揮者クラウディオ・アバドのアシスタントを務め、息子のカール(カルロス)は、父エーリヒ以上に偉大な指揮者として20世紀にその名を轟かす、カルロス・クライバーです。
順調にキャリアを重ねたクライバーですが、やがて彼の元にもナチス政権の暗い影が忍び寄ります。ナチスの政策に断固として反対の立場を取ったクライバーは、ドイツ国立歌劇場の常任指揮者の職を辞し、アルゼンチンのブエノスアイリスへ向かうことに。
その後1936年から49年まで、テアトロ・コロン歌劇場指揮者を務めたほか、1944年から47年にはハバナ・フィルの指揮者として音楽に携わりました。
いずれにしても、ナチスによる人種差別政策に対するクライバーの強い意思がここから伝わってきます。
復帰から晩年
1948年、ロンドンフィルとの共演でヨーロッパに復帰したクライバーは、ロンドンを拠点として指揮活動を再開し、再び各地で公演を行います。1950年代初頭になると、東ドイツの要請によりベルリン・フィルハーモニー管弦楽団に復帰したものの、その後すぐ招待は取り下げられ、これをきっかけに、クライバーは二度と東ドイツに戻ることはありませんでした。
余談ですが、クライバーはこれより前の1935年にロンドン交響楽団でイギリスデビューしており、1938年には指揮者トマス・ビーチャムの招きにより、コヴェント・ガーデン(ロンドンの中心街)の演奏会にも登場しています。
常任指揮者としての立場を失ったものの、クライバーの人気はすでに世界的なものになっており、その後もヨーロッパ各国にて客員指揮者としてその手腕を発揮しています。
その後も演奏旅行で忙しい毎日を送っていたクライバーですが、1956年1月に演奏旅行中のスイス・チューリッヒにてこの世を去りました。享年65歳。この日はクライバーが得意としていたモーツァルト生誕200年記念日だったそうです。
エーリヒ・クライバーの性格を物語るエピソードについて

エーリヒ・クライバーのエピソードについて2つ紹介します。クライバーは自分にも他人にも妥協を許さない指揮者でした。また新ウィーン楽派のアルバン・ベルクとは、公私において交流を深めています。
厳しい指導
20世紀初頭の指揮者たちにありがちなことですが、クライバーの楽団員に対する指導は厳格なものでした。彼の練習はプロの演奏家も音を上げるほどだったそうで、その指導法は「いかなる反論もはねつける」やり方だったと言います(その代表格がアルトゥール・トスカニーニです)。
ある日、R・シュトラウスのオペラ『薔薇の騎士』を録音していたときのこと。旋律をヴァイオリンのG線で弾くように楽団員に指示したクライバーですが、楽団員が「その箇所はG線が響かない」と反論します。
それに対しクライバーは「第2ヴァイオリニストなどから、ご意見を承ったりなどしない」と突っぱねたそうです。
今でこそ、指揮者と楽団員は民主的なやりとりとなりましたが、クライバーの熱い思いと厳しさが垣間見られるエピソードですね。
友人アルバン・ベルクとの思い出
モーツァルトやベートーヴェンなどの古典派からR・シュトラウスなどのロマン派作品まで幅広いレパートリーをこなしたクライバー。そんな彼は、20世紀に登場した無調音楽や十二音技法にも理解を示しました。なかでも新ウィーン楽派の作曲家アルバン・ベルクとは友人として交流を深め、代表作『ヴォツェック』の初演を務めました。
ナチス・ドイツをめぐる関係において、一時期その関係は悪化したものの(クライバーの勘違いが発端ですが)、その関係はベルクが亡くなるまで続いたと言います。
もしクライバーがベルクの作品に理解を示さず、指揮することを拒否していたら『ヴォツェック』は今頃忘れさられていたかもしれません。作品の初演は大論争を巻き起こしたものの、クライバーが音楽史において重要な役割を果たしたのは間違いないでしょう。
エーリヒ・クライバーの演奏風景
楽団員に対するクライバーの指導は、大変厳しいものであったと伝えられています。
しかし彼の指揮した作品は威厳に満ち溢れ、揺るぎないものでもありました。とくにベートーヴェンの威風堂々たる演奏は名盤に数えられ、現在でも根強いファンを獲得しています。
その他、モーツァルト作曲のオペラ『フィガロの結婚』にも定評があります。今回はベートーヴェンの『交響曲第5番運命』をお楽しみください。
まとめ
エーリヒ・クライバーの生涯について解説しました。彼は音楽に対して真摯に取り組んだ人物であり、それと同時に平和を願う強い信念の持ち主だったようです。クライバーの演奏を聴いていると、厳しさの中にある深い愛情が伝わってきます。そしてこの偉大なる指揮者の功績は、息子のカルロス・クライバーへと受け継がれます。
これまでエーリヒ・クライバーの演奏を聴いたことがない方は、この記事を機会にぜひ彼の演奏を聴いてみてはいかがでしょうか。


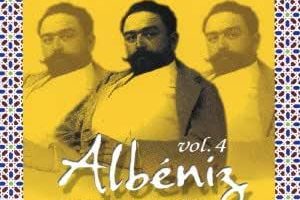

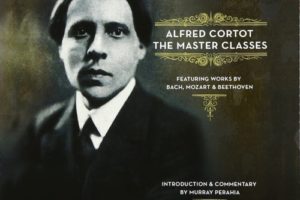



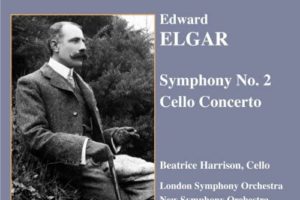



コメントを残す